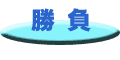
・昨日三日目の相撲は賽日といい顔触れも宜ければ、見物人四千の上に出でたり。
・番数のうち高千穂に大達は、高千穂が少しく後れて立つと見えしが、大達は押し切り土俵の際にて突き出す鉄砲に高千穂は踏切り大達の勝。
・若島に出来山は難なく立合い、若島が一杯に突掛け来る所を出来山は見事「ハタキ」、若島は前日の如く体を前へ流し、手も膝も砂に付き出来山の勝。
・(以下中入後)立田野に稲川は見事に立合い、立田野は右を差して廻しを取り、左を相手の腋にあてると其のまま押し切りて立田野の勝。
・西ノ海に緋縅は、立派に立合い双方左を差して渡り合いつ揉合いもしが、勝負付かず水入りしに緋縅の方に痛みありて引分。
・上ヶ汐に司天龍は、上ヶ汐余程後れて立合いしが雷の如く荒れて突掛かりしに、司天龍はたぢたぢと後ずさりしアワヤ踏み切らん勢いなれば、土俵を廻らんとなせし機に上ヶ汐は右手にて相手の顎を支え其のまま押し切りて上ヶ汐の勝ちしは是れ「ヤハズ」の一手にして実に目覚ましき働きなりし。
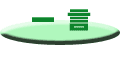
【司天龍】
入幕4場所目ながら、ここまで好成績を続けて新関脇に昇進。しかしこの日は猛烈な咽喉輪に押されて完敗しました。「矢筈」は相手の腋の下を押すものを指しますが、その変形版という解釈でしょうか。上ヶ汐の気合が光る相撲でした。
【出来山】
ベテランの大纒は二枚鑑札となり、今場所から出来山に改名。大関・若嶋をはたき込みで破りました。若嶋は二日続けてはたきで敗れ、やや脆さが出ています。
 西関脇・司天龍芳五郎
西関脇・司天龍芳五郎
明治15年春場所星取表