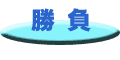
○回向院大相撲
・昨日の三日目は大景気にて佐々木副島吉井の三伯爵、蜂須賀侯爵、安藤議官その他貴顕方をも見受けたり。
・緋縅に龍門は、立上り龍は諸差しとなりて押出さんとせしを、敵は極め付けながら体をかわし櫓にて緋縅の勝は珍しき事に思わる。
・千羽ヶ嶽に伊勢ノ濱は、二本差しヨリて伊勢の勝。
・真力に綾浪は、立上り綾は左を差し右にて敵の前袋を取り無二無三にヨラんとする時、真は右をハヅに構い、突落して真の勝。
・鬼ヶ谷に上ヶ汐はいづれも巧者の力士なれば、立上り二三合突合い上は右を差して始終下手投けに行きしが、鬼はイヤダと左を差し切返して鬼に団扇の上がりたるも上は敵に踏切りありとて物言付きて預り、時に上ヶ汐の眼の上に大なる瘤が出来たるは突合う際鬼の頭が当たりしゆえなりと、何にせよ力士中にても鬼は眼の上の癌なりと云い居りしが果して。
・知恵ノ矢に西ノ海は西右を引張りナタにて攻め付けヨラんとする時、イヤダとこれを防ぎしより突放して西の勝。
・剣山に相生は、立上り突合い左四ツにて張合う時、相は足クセに行きしが解いて合四ツ大相撲となりたるに、満場鯨声は暫時鳴りも止まざりき、さて力士は必死となりて競ううち水入り、再び揉合い引分は充分なりき。
・平ノ戸に藤ノ戸は、ヨイショと云いながら突掛け行きしに、平はこれを引張り込みし時藤腰の浮きたるより待ったと云う間もなく突出して平の勝なりき、然るに藤は土俵を下らず待ったと云うを角觝にせしは不都合なりと、一人にて苦情を云い張り中々に下らざるより、溜りの阿武松が種々説諭せしも下らざるより四本柱の関ノ戸清見潟までが是非なく柱を離れ藤に説諭を為しようやくに下りたるが、昨今負け力士に苦情流行し、ために時間を費やし他の相撲の妨げともなり観客の迷惑ともなれば、是らの悪弊はきっと矯正したき事なり。
・平石に泉瀧は左四ツ、ウッチャリて平石の勝。
・海山に千年川は、立上り千は右を差したるに其の手を押さえ逆にヒネリて海山の勝。
・鞆ノ平に真鶴は、突出して鞆の勝。
・八幡山に嵐山は、此の日第一の取組なれば勝負如何あらんと注目し居るに、力士は充分に仕切り立上り左四ツとなり、攻合ううち合四ツとなりこの時水入りて後再び競い合いしが、取り疲れ引分となりたり、或る人は此の相撲一番にて斯く人気も引立ち居るに、わずか挑みし迄にて取り疲れたりとて引分は甚だ不満足の事なりと呟き居りしが、同社会にて此の相撲に勝負を付けざるは畢竟客を招く一の権謀なるべしと思わる。
・大鳴門に高見山は、右四ツとなりて鳴門押出さんと攻め付る時、土俵際にて清見首投げに行きしもヨリ切りて鳴門の勝。
・若湊に一ノ矢は、互いに仕切り直せし事十余度にして、見物は何時立上る事ならんと罵詈を為すものもありしが、力士はようやくに立上り一は極め付けんとでも思いしか、しきりに敵を引張り込まんとせしに、若はそうはさせじと右をハヅに構い左を差しながら押し切りて若の勝となりしより、満場拍手喝采の声中々にして実に破るるばかりの有様なりき。
・(昨日の紙上、真鶴に千羽ヶ嶽は真鶴の勝とせしが預りの誤り)
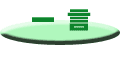
新入幕の若湊が関脇一ノ矢を破り殊勲。昨日の殊勲者相生も大関と互角の相撲で盛り上げました。この日も引き分け・預かり・物言い等いろいろありましたが、引き分けで白黒つけないのは興行上の理由もある、という見方もあるようですね。いずれにしろ両者力を出し切った相撲をファンが望むのは昔も今も変わりません。
明治21年春場所星取表
SECRET: 0
PASS: be83e113aeeec3717846a8131ae8370e
こんばんは。こちらでは、はじめまして。
随分前に、白鵬の星取表についてメールで質問させていただいたマレーシア在住の者です。その節は大変お世話になりました。ご指南いただいたとおり、無事、決まり手もわかりました。ありがとうございました。
こちらのレトロ記事。大変興味深く拝見しております。質問があります。今では「白房下」などと言う表現で、力士が動いた場所などを表現しますが、戦前は柱でしたから、現在のような表現はないですよね?単に、東西南北で表現していたのでしょうか?記事を拝見する限り、手さばきが主で、特にどの方向に動いたなどの様子が書かれていないような気がするのですが、どうでしょうか?
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
どうもお久しぶりです(・ω・)ノ
現在でも正面土俵とか東土俵とか使いますが、今のところそういう描写は出てきていませんね。手元には大正初めまでの記事は揃っているのですが、ざっと見たところあまり見かけません。すみずみまで読んだわけではないので、これから更新していく中で出てくるかも・・・更新ネタはいくらでもあるのですが、入力する手間暇の問題で更新が滞っていてすみません(-ω-)来週も1週間不在にしますが、その後には少しずつ復活する予定ですので。