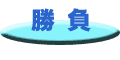
・昨日回向院の相撲は観客二千三百二拾人にて実に三日目には意外の大入なりし。
・中入前、柏戸に司天龍の取組は余程面白かりし取口なりしかど、引分となりしゆえこれを略す。
・上ヶ汐と武蔵潟の勝負には上ヶ汐は少しく立ち後れしが、いかなる隙のありしにや立ち声を合せて立上るや否やただちに下へ潜りて左手を差し右手を伸して前袋を取りしを、武蔵潟は是こそ大切なりと両手を上ヶ汐の首に搦みて締め付たる有様は、さながら蒼鷹の鶯児をつかみし如くなりし、この時見物はどっとどよみ渡りしが、武蔵潟は其のまま上ヶ汐を抱えて持ち出さんとせしに、上ヶ汐は右足を相手の左足に搦みて反りしかば、却って武蔵潟は見事に「河津」に掛けられついに上ヶ汐の勝となりたり。
・中入後響矢と荒角は随分立派な立合い、二ツ三ツ突き合ううち響矢は下へ抜け右手を差して三ツを取り、左手にて相手の右手に受けて居たりしが一引き引き、自分の体を沈めしかば荒角は事も見事にかぶられ負となりたり。
・両大関若島、梅ヶ谷は当日まで土付かず。
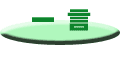
【武蔵潟】
身長209cmあったという超巨漢。上ヶ汐の身長は分かりませんが、この時代の力士は170cm台前半が標準ですので、相当な身長差だったでしょう。低く潜られてしまいましたが、武蔵潟はまるでタカがウグイスの子を捕まえるように相手の首筋を締め上げ、土俵際に持って行きます。しかし最後は上ヶ汐が河津掛けで勝利。小よく大を制しました。
明治14年春場所星取表